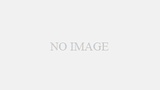文化の日とは
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年公布・施行の祝日法により制定。1946年11月3日に新憲法が公布されたことを記念して定められた祝日で、もともとは明治天皇の誕生日を祝う「天長節」、昭和初期までは「明治節」と呼ばれる祝日だった。皇居では毎年この日に文化勲章の受章式が執り行われる。
戦前、11月3日は明治天皇の誕生日を祝う「明治節」という祝日でした。明治時代にはその誕生日を祝う「天長節」として扱われており、大正時代に入ってからは「明治節」と改められました。戦後、この日が国民の祝日として残されることになり、日本国憲法の公布日であることにちなみ、1948年に「自由と平和を愛し文化をすすめる日」として「文化の日」が制定されました。
5月3日は日本国憲法の施行日を記念する「憲法記念日」で、11月3日は日本国憲法の公布日であることから「文化の日」と制定されました。本来、GHQは11月3日を憲法記念日にすべきと考えていましたが、天皇との関連を避けるため、公布日を文化の日とし、施行日を憲法記念日としました。